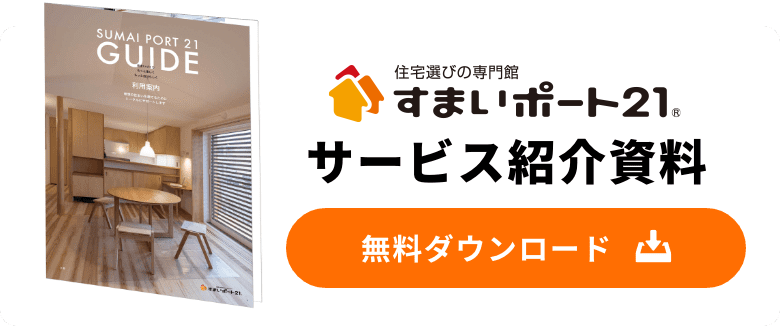【2025年1月最新】土地ありで理想の家を建てる:費用、注意点、流れを徹底解説
公開日 : 2025.1.1
お役立ち情報土地をお持ちの方が家を建てる際、費用はどのくらいかかるのか、どのような点に注意すべきか、具体的な流れはどうなのかなど、様々な疑問があるかと思います。
この記事では、土地ありで家を建てる際の費用相場、費用の内訳、流れ、注意点などを詳しく解説します。
目次
土地ありで家を建てる際の費用相場と内訳

全国平均と地域別の費用相場
土地ありで家を建てる際の全国平均費用は、一般的に建物の本体工事費、別途工事費、諸経費を合わせて、約3,000万円から5,000万円程度が目安となります。
ただし、この金額はあくまで目安であり、建物の構造、広さ、デザイン、使用する素材、設備のグレード、さらには依頼する業者によって大きく変動します。
地域別の費用相場を見てみると、都市部では土地の価格が高い影響から、建築費も高くなる傾向があります。
一方、地方都市や郊外では比較的費用を抑えられる可能性があります。
例えば、東京都内と地方の県庁所在地を比較すると、数百万円単位で費用が変わることもあります。
そのため、ご自身の住む地域における相場をしっかりと把握することが大切です。具体的な相場を把握するためには、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することを推奨します。
また、地域の工務店や住宅展示場などで情報収集を行うのも有効な手段です。
本体工事費、別途工事費、諸経費の詳細
家を建てる際には、大きく分けて「本体工事費」「別途工事費」「諸経費」の3つの費用が発生します。
本体工事費とは、建物の基礎、骨組み、内装、外装など、建物そのものを建てるための費用です。
これは総費用の約70%を占める最も大きな割合になります。具体的には、基礎工事、木工事、屋根工事、外壁工事、内装工事、電気工事、給排水設備工事などが含まれます。
別途工事費は、建物本体以外に必要な工事の費用で、外構工事、地盤改良工事、解体工事などが該当します。
例えば、庭をつくるための整地や駐車場を作るための舗装、古家を解体する場合の費用などです。地盤が弱い場合は、地盤改良工事が必要になり、追加費用が発生します。
また、既存の建物を取り壊す場合には、解体工事費も考慮に入れる必要があります。諸経費は、住宅ローンを利用する際の手数料、登記費用、火災保険料、不動産取得税、各種税金など、建物本体以外にかかる費用です。これらの費用は、現金で支払う必要があり、総費用の約10%程度を占めます。
これらの費用を事前に把握し、予算計画を立てることが非常に重要です。
土地なしの場合との費用比較
土地ありで家を建てる場合と、土地なしで家を建てる場合とでは、費用に大きな違いがあります。
土地なしで家を建てる場合、まず土地を購入する必要があるため、その費用が建築費用に大きく上乗せされます。
土地の価格は、地域や立地条件によって大きく変動しますが、都市部では高額になることが多く、土地代だけで数千万円かかることも珍しくありません。
一方、土地ありの場合は、土地の購入費用がかからないため、その分費用を抑えることができます。
例えば、同じ広さの家を建てる場合でも、土地代が1,000万円かかる地域と、土地代がかからない場合とでは、総費用に1,000万円以上の差が出ることもあります。
また、土地なしの場合、土地探しから始める必要があり、時間も手間もかかります。土地ありの場合、これらの手間を省くことができるため、よりスムーズに家づくりを進めることができます。
しかし、土地ありの場合でも、既存の建物が建っていたり、地盤に問題がある場合は、別途費用が発生する可能性があるため、注意が必要です。
土地ありで家を建てる際の注意点

土地の地目と農地転用の注意点
土地には、宅地、田、畑、山林など、様々な「地目」が存在します。
地目とは、その土地がどのような用途に使われているかを示すものです。宅地は建物を建てることが許可されている土地ですが、田や畑などの農地は、原則として建物を建てることはできません。
もし農地に家を建てたい場合は、「農地転用」の手続きが必要になります。農地転用とは、農地を宅地など、農地以外の用途に変更することを指します。
この手続きは、農業委員会や都道府県知事の許可が必要であり、非常に複雑で時間がかかる場合があります。
農地転用の許可を得るためには、転用する理由や計画が適切であること、周辺の農業環境に悪影響を与えないことなど、様々な条件を満たす必要があります。
また、転用許可を得た後も、農地転用に伴う税金が発生する場合があります。そのため、農地に家を建てたい場合は、専門家や行政機関に相談し、事前にしっかりと調査を行うことが重要です。
特に、相続した土地が農地の場合、この手続きが必要になることが多いので、注意が必要です。
相続した土地に家を建てる際の注意点
相続した土地に家を建てる際には、いくつかの注意点があります。
まず、相続登記が完了しているかを確認することが重要です。相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
この手続きが完了していないと、法的に土地の所有権を証明することができず、家を建てることができません。
相続登記の手続きは、相続人全員の合意が必要となるため、事前に相続人同士で話し合い、協力して手続きを進める必要があります。また、相続税の問題も考慮に入れる必要があります。
相続した土地の評価額によっては、相続税が発生する場合があります。相続税の計算は非常に複雑であり、税理士などの専門家に相談することを推奨します。
また、相続した土地が農地の場合、前述の農地転用の手続きが必要になる場合があります。さらに、相続した土地に抵当権が設定されている場合もあります。
この場合は、抵当権を解除してからでないと家を建てることができません。事前にこれらの問題点をしっかりと確認し、スムーズな家づくりを進めることが重要です。
地盤調査と境界線の確認
家を建てる前には、必ず地盤調査を行うことが重要です。
地盤調査とは、土地の地盤の強度や状態を調べることで、建物を安全に支えることができるかを確認するためのものです。
地盤が軟弱な場合、地盤改良工事が必要になり、追加費用が発生する可能性があります。地盤調査の方法には、ボーリング調査、表面波探査法、スウェーデン式サウンディング試験などがあります。
専門業者に依頼し、適切な方法で調査を行うことが重要です。
また、隣地との境界線の確認も非常に重要です。境界線があいまいな場合、後々トラブルになる可能性があります。
境界線を明確にするためには、測量士に依頼し、境界確定測量を行う必要があります。境界確定測量では、隣接する土地の所有者と立ち会い、境界杭を設置します。
この手続きを怠ると、後々隣人との間でトラブルになる可能性があるため、必ず行うようにしましょう。
これらの調査や確認を怠ると、後々大きなトラブルや追加費用が発生する可能性があるため、事前にしっかりと行うことが大切です。
家を建てる流れと具体的な手順
予算決定から住宅ローン本審査まで
家を建てるためには、まず最初に予算を決定することが重要です。
予算を決める際には、自己資金だけでなく、住宅ローンの利用も検討する必要があります。
住宅ローンを借りるためには、まず金融機関に事前審査を申し込む必要があります。事前審査では、借り入れ希望額や返済期間、年収などを基に、おおよその借入可能額を算出します。
事前審査の結果を踏まえて、住宅ローンの種類や金利タイプを比較検討し、最適なローンを選ぶようにしましょう。
住宅ローンの事前審査に通ったら、次に本審査を申し込みます。本審査では、より詳細な情報や書類が必要になり、審査も厳しくなります。
住宅ローンの本審査に通ったら、住宅ローンの契約を結び、融資を受ける準備を始めます。
予算を決める際には、建物の本体価格だけでなく、諸経費や別途工事費も考慮に入れる必要があります。
また、家具や家電の購入費用なども見込んでおきましょう。無理のない返済計画を立てることで、安心して家づくりを進めることができます。
施工会社選びとプラン打ち合わせのコツ
家づくりで最も重要な要素の一つが、信頼できる施工会社を選ぶことです。
施工会社には、ハウスメーカー、工務店、設計事務所など、様々な種類があります。
それぞれの特徴を理解し、自分の希望や予算に合った業者を選ぶようにしましょう。
ハウスメーカーは、全国展開している大手企業が多く、品質やアフターサービスに定評があります。
工務店は、地域密着型で、自由度の高い家づくりが可能です。設計事務所は、デザイン性の高い家を建てたい場合に適しています。
施工会社を選ぶ際には、複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することが重要です。
見積もり内容だけでなく、業者の担当者の対応や実績、評判なども確認しましょう。
施工会社が決まったら、プランの打ち合わせを行います。打ち合わせでは、自分の希望やライフスタイルを具体的に伝えることが大切です。
間取りやデザイン、設備、素材など、細部にわたって打ち合わせを行い、理想の家を実現しましょう。
打ち合わせの際には、積極的に質問をし、納得のいくまで話し合うことが重要です。
工事請負契約から引き渡しまで
施工会社とのプランがまとまったら、工事請負契約を結びます。
工事請負契約とは、施工会社が建物を建築し、引き渡すことを約束する契約です。
契約書には、工事内容、工期、請負金額、支払い条件などが記載されています。
契約書の内容をしっかりと確認し、不明な点があれば、施工会社に質問し、納得した上で契約を結ぶようにしましょう。
契約締結後、いよいよ工事が開始されます。工事中は、定期的に現場に足を運び、進捗状況を確認しましょう。
何か問題があれば、施工会社に速やかに連絡し、対応を求めることが重要です。
工事が完了すると、施工会社による完了検査が行われます。完了検査に合格したら、次に施主検査を行います。
施主検査では、建物の仕上がりを細かくチェックし、不具合があれば、施工会社に補修を依頼します。
施主検査が完了し、問題がなければ、いよいよ建物の引き渡しとなります。
引き渡しの際には、建物の鍵や保証書などを受け取り、契約内容と照らし合わせ、間違いがないか確認しましょう。
引き渡し後も、アフターサービスについて確認し、長く安心して暮らせるようにしましょう。
費用を抑えるためのポイント

家の形状をシンプルにする
家の形状をシンプルにすることは、建築費用を抑えるための有効な手段の一つです。
複雑な形状の家は、材料費や施工費が高くなる傾向があります。
例えば、凹凸の少ないシンプルな箱型の家は、使用する材料や工事の手間を減らすことができるため、費用を抑えることができます。
また、屋根の形状も、切妻屋根や片流れ屋根など、シンプルな形状にすることで費用を抑えることができます。
一方、複雑な形状の屋根は、施工の手間が増え、材料費も高くなる傾向があります。
家の形状をシンプルにする際には、デザイン性も考慮に入れる必要があります。
シンプルな形状でも、素材や色使いを工夫することで、おしゃれな家を建てることができます。
例えば、外壁に木材を使用したり、アクセントカラーを取り入れたりすることで、個性を出すことも可能です。
家の形状をシンプルにすることは、費用を抑えるだけでなく、メンテナンス性も高める効果があります。
シンプルな形状の家は、メンテナンスがしやすく、将来的な維持費を抑えることができます。
希望条件に優先順位をつける
家づくりを始める前に、まず自分の希望条件をリストアップし、それぞれの優先順位をつけることが重要です。
すべての希望を叶えようとすると、予算オーバーになってしまう可能性があります。
そこで、絶対に譲れない条件と、妥協できる条件を明確にすることが大切です。
例えば、間取りや広さ、設備、デザインなど、様々な希望条件があると思いますが、それぞれの重要度を考慮し、優先順位をつけるようにしましょう。
優先順位の高い条件を優先的に実現し、優先順位の低い条件は、予算やその他の条件に応じて妥協することも検討しましょう。
例えば、キッチンのグレードを少し下げたり、収納スペースを減らしたりすることで、費用を抑えることができます。
また、将来的なライフスタイルの変化も考慮に入れ、本当に必要なものを見極めることが重要です。
例えば、子供が独立した後のことを考えると、子供部屋の広さを少し小さくすることも可能です。
希望条件に優先順位をつけることで、無駄なコストを削減し、効率的な家づくりを進めることができます。
複数社を比較検討する
家づくりを成功させるためには、複数のハウスメーカーや工務店に見積もりを依頼し、比較検討することが非常に重要です。
複数の業者から見積もりを取ることで、それぞれの業者の強みや弱みを把握することができます。
見積もりを比較検討する際には、金額だけでなく、工事内容や使用する材料、保証内容なども確認しましょう。
また、業者の担当者の対応や、過去の実績なども参考にすると良いでしょう。
それぞれの業者によって、得意とする工法やデザインが異なるため、自分の希望に合った業者を選ぶことが大切です。
例えば、デザイン性の高い家を建てたい場合は、設計事務所に依頼することも検討しましょう。
見積もりを比較検討する際には、価格交渉も積極的に行いましょう。
場合によっては、同じ内容でも、数百万単位で金額が変わることもあります。
また、キャンペーンや割引を利用することで、費用を抑えることも可能です。
複数の業者を比較検討することで、自分にとって最適な業者を見つけることができ、満足のいく家づくりを実現することができます。
まとめ
土地ありで家を建てる際には、費用、注意点、流れについてしっかりと理解しておくことが重要です。
この記事では、費用相場、注意点、家を建てる流れ、費用を抑えるためのポイントを詳しく解説しました。
費用については、全国平均や地域別の相場を把握し、本体工事費、別途工事費、諸経費の内訳を理解することが大切です。
また、土地の地目や農地転用、相続した土地に関する注意点も確認しましょう。
家を建てる流れとしては、予算決定から住宅ローン本審査、施工会社選び、プラン打ち合わせ、工事請負契約、引き渡しまで、各段階で注意すべき点があります。
費用を抑えるためには、家の形状をシンプルにすることや、希望条件に優先順位をつけること、複数社を比較検討することが有効です。
この記事を参考に、ご自身の理想の家づくりを成功させてください。
カテゴリー
タグ